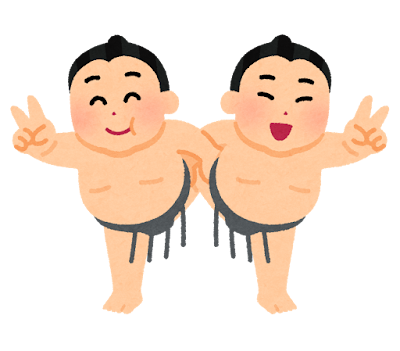こんにちは。りんご桜です。
相撲観戦のクライマックスを彩る華やかな儀式、弓取り式(ゆみとりしき)。
結びの一番を制した力士の代わりに、幕下力士が弓を手に舞い、その勇姿を披露します。
弓取り式を見ると、「今日の取組みが終わってしまった。早く明日にならないかな」と思ってしまうのは私だけでしょうか。
今回は、この伝統ある弓取り式について、務める力士など、その由来や意味、様々な角度から深掘りしていきます!
弓取式の力士の給料(手当)は?
弓取り式を行う力士には、1場所につき9万円の手当が支給されています。
「へぇ〜、意外ともらえるんだな」って思いました?でも、これには深いワケがあるんです。
「月給」がもらえるのはエリートだけ!
大相撲の世界は、想像以上に超・実力主義。
実は、月給(ボーナス込)がもらえるのは、十両以上の「関取」だけなんです。
関取(十両以上): 毎月の給料あり。年収1,000万円オーバーも!
力士養成員(幕下以下): 月給は「ゼロ」。
じゃあ、幕下以下の力士たちはどうやって食べているのかというと、年6回の本場所ごとにもらえる「場所手当」だけが頼りなんです。
幕下以下の「場所手当」一覧表
その気になる金額がこちら。
| 階級 | 1場所あたりの手当 | 年収換算(手当のみ) |
| 幕下 | 150,000円 | 900,000円 |
| 三段目 | 100,000円 | 600,000円 |
| 序二段 | 80,000円 | 480,000円 |
| 序の口 | 70,000円 | 420,000円 |
見てください、このリアルな数字。
序の口だと、1場所(2ヶ月分)で7万円。月あたりに直すとたったの3万5,000円です。
ちゃんこ(食費)や住居費は相撲部屋が持ってくれるとはいえ、自分のお小遣いや日用品を買うには、かなり厳しい金額ですよね。
だから「9万円」の重みがすごい
ここで最初の話に戻ります。弓取り式の手当は1場所9万円。
もし幕下の力士が選ばれたら、場所手当15万円+弓取り手当9万円=24万円!
なんと、本来の手当が1.6倍に跳ね上がる計算になります。三段目の力士なら、ほぼ倍増です。あの勇壮な舞の裏側には、若手力士たちの生活を支える「超・貴重なボーナス」という側面もあったんですね。
弓取式の力士は誰がやるの?
そもそも弓取り式ができるのは、選ばれしエリート若手。
基本的には「横綱と同じ部屋の幕下以下の力士」が担当します。 (もし横綱が休場しちゃった場合は、大関の部屋から選出されるというルールも!)
彼らは、結びの一番が行われている間、土俵の下(向正面)で静かに自分の出番を待っています。この「待機」の瞬間から、すでにドラマは始まっているんです。
「東が勝つか、西が勝つか」でルートが変わる!
ここが一番の注目ポイント。 実は、弓取り力士が土俵に上がる方向は、結びの一番で勝った力士のサイドからと決まっているんです!
東の力士が勝った場合: 東から土俵へ
西の力士が勝った場合: 西から土俵へ
勝った力士に代わって「勝者の舞」を披露するわけですから、花道も勝者と同じ側を通るんですね。
動作も「左右逆」になる!?
土俵に上がってからの動きも、実はよーく見ると違いがあります。 弓を頭上で回し、左右に八の字に振る華麗な動きの途中で、**「弓で土俵をすくうような所作」**がありますよね?
ここでも、勝った力士が東なら**「東側」を、西なら「西側」**を先にすくうような動作を行うんです。 そして最後に、弓を肩に担いでドッシリと四股を踏む……。
毎日同じことをやっているように見えて、実はその日の結果に合わせて、瞬時に動きをスイッチさせているんです。プロフェッショナルですよね!
観戦がもっと楽しくなるチェックポイント!
「今日はどっちが勝つかな?」と予想しながら、結びの一番を見た後に、 「お、今日は西が勝ったから西から上がってきたぞ!」 と確認するだけで、通の楽しみ方ができてしまいます。
ただカッコいいだけじゃなく、勝負の結果を背負って舞う「弓取り式」。 そんな細かい所作に注目してみると、大相撲観戦がもっともっと奥深くなりますよ!
弓取式の力士は誰?現在は??
今回は、土俵入りの後、結びの一番の前に披露される弓取式で活躍している力士は、
二所ノ関部屋の羅漢児 寛大(らかんじ かんだい)です。
羅漢児、弓取り式力士に抜擢!
羅漢児が弓取り式を務めることになったのは、2025年夏巡業での出来事でした。それまで弓取り式を担っていた花の海関が怪我をしたため、急遽その代役として羅漢児関が抜擢されたのです。そして、2025年9月場所が彼の本場所デビューとなりました。
「羅漢児」という四股名の由来
四股名には、深い意味が込められています。
「羅漢寺」は、羅漢児の出身地である大分県中津市にある有名なお寺、羅漢寺に由来しています。
「羅漢」とは、仏教において一切の煩悩を断ち切り、悟りを開いた、尊敬されるべき存在を指します。羅漢児関は、この境地に近づけるようにという願いを込めて、この四股名をつけられました。しかし、まだ修行中の身であることから、「児(こ)」という文字が付けられています。いつか「羅漢」にふさわしい力士になったときには、さらなる改名も計画されているのかもしれませんね。
「寛大」という下の名は、二所ノ関親方の名前から一文字もらい、言葉の通り「器の大きな力士」になってほしいという期待が込められています。
このように、羅漢児の四股名には、親方の期待と彼の成長への願いが詰まっています!
弓取式の由来は?意味は?
そのルーツを辿ると、なんと平安時代までさかのぼります!
昔、弓は「最強のプレゼント」だった!?
平安時代、弓矢は単なる武器ではなく、最強の「武力の象徴」でした。 当時の相撲の節会(せちえ)などで、勝った力士を称えるために「弓」を贈ったことが、今の弓取り式の始まりだと言われています。
つまり、あの華麗な舞は、もともとは「優勝おめでとう!君は最強だ!」という表彰式のようなものだったんですね。
千年以上のバトンタッチ
平安時代から令和の今まで、1000年以上の時を超えて受け継がれているなんて、ちょっと鳥肌が立ちませんか?
-
戦国時代も、江戸時代も、
-
そして激動の明治・昭和も、
ずっと変わらず「勝者を称える儀式」として、力士たちが弓を振り続けてきたわけです。私たちが今日国技館で、あるいはテレビの前で見ているあの光景は、平安貴族が見ていた景色と繋がっているのかもしれません。
だからこそ、大切にしたい「伝承の心」
毎日、結びの一番の後に当たり前のように行われている弓取り式。 でも、その背景には「勝利を称え、平和を願う」という、日本人がずっと大切にしてきた心がギュッと詰まっています。
「歴史があるから価値がある」というよりは、「みんなが大切にしてきたから、今日まで残っている」。そう思うと、あの弓を回す所作一つひとつが、より神聖で、より尊いものに見えてきますよね。
弓取式の意味は?
弓取り式には、3つの意味が込められていると考えられています。
1. 「おめでとう!」を形にした勝利の祝賀
一番分かりやすいのが、結びの一番で勝った力士への祝福です。 あの力強く、かつしなやかな弓の動きは、まさに「勝利の喜び」の表現!
勝った力士に代わって、弓取り力士が土俵上でその栄誉を全身で表現しているんです。あのダイナミックな八の字は、勝利のエネルギーそのものなんですね。
2. 「ありがとうございます」という神様への感謝
大相撲は、もともと神様に捧げる「神事」として発展してきました。 だからこそ、勝敗の結果だけでなく、「今日も無事に場所が終わりました、ありがとうございます」という神様への感謝が込められているんです。
土俵をすくうような仕草も、大地の神様に敬意を払っているかのよう。ただのスポーツイベントではなく、祈りの儀式としての側面が、あの静謐な空気感を作っているんですね。
3. 千年のバトンを繋ぐ「伝統の継承」
そして何より大切なのが、「文化を後世に繋ぐ」という役割です。 平安時代から続くこの儀式を、現代の力士たちが寸分違わず再現し続けること。
これこそが、相撲が「国技」と呼ばれる所以(ゆえん)です。 弓取り式が毎日行われることで、私たちは1000年前の日本人の心に触れ、それをまた次の世代へと手渡していく。まさに、時空を超えたバトンタッチかもしれませんね!
まとめ
●弓取り式を行う力士には1場所当たり9万円の手当が支給されます(年6回)。
●弓取り式を行う力士は、横綱と同じ部屋の幕下以下またはの力士から選ばれます。
※横綱がの休場の場合は大関の部屋から選ばれます。
●弓取式の力士は二所ノ関部屋の羅漢児です。
● 勝利の祝賀・神への感謝・伝統の継承3つの意味が込められています。
いかがだったでしょうか?
弓取り式は、単なる儀式ではなく、相撲の歴史や文化を象徴する重要なものです。
弓取り式は、まさに大相撲の「美学」が詰まった最高のフィナーレです。 これからもこの素晴らしい伝統が、100年、500年、1000年と続いていくことを願わずにはいられません。
みなさんも、次に弓取り式を見るときは、ぜひ千年前に思いを馳せてみてくださいね。
きっと、いつもより少し深く、感動できるはずですよ!